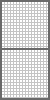自分で襖を張り替えられる?
こんにちは!襖張替え職人の栗田です。本日はふすまの張り替えをお客様ご自身で行う際の注意点をブログにしてみました。まずは自分でやってみたい!という方の参考になれば幸いです
準備をしっかりと行う
- 必要な道具(のり、ボンド、カッター、施工台、バケツ、スポンジ、定規、バール、トンカチなど)を事前に準備しておく。
- 新しいふすま紙も選んでおく。種類によって雰囲気が大きく変わるため、部屋のインテリアに合うものを選ぶ。
⇒まずは下準備から。正直なところこの部分がとっても大切で全体の5割を占めています。
古いふすま紙を丁寧に剥がす
- 枠を外す(なお、板襖や段ボール、発泡スチロールの襖は枠は外れません)
- 古いふすま紙は、濡れタオルなどで湿らせてから剥がすと綺麗に取れやすい。
- 無理に引っ張ると下地が痛む可能性があるため、丁寧に作業をする
⇒古い襖を剥がさずに上から巻きつける施工方法もありますが、判断に迷ったらまずはキレイに剥がしきりましょう
下地の清掃と補修
- 古い紙を剥がした後は、下地のチェックを行い、汚れやホコリをきれいに拭き取る。
- 破損や凹凸がある場合は、補修を行う。
⇒下地は軽微な凹みはマスキングテープなどで塞ぎますが大きな穴は大穴補修紙や雲華紙を裏返して一枚貼り付けて私は補修しています
のりの選択と使用方法
- ふすま紙専用ののりを使用すること。一般的なのりとは異なる場合があるので注意。
- のりは均等に薄く塗る。塗りすぎると紙が波打つ原因になる。
⇒のりは障子用を使う職人もいますし、私は木工用ボンドを使う派です。紙、本体の劣化状況にあわせて選びます
ふすま紙の貼り方
- 紙を水で均等に濡らして本体に覆いかぶせます
注意1)壁紙クロスではないのでこの段階でピンと張ってしまうと本体が反ったりします
注意2)板襖の場合、施工方法が異なります
注意3)板襖の場合、全面のりで張るか、水張りを採用するかは本体の状況で変わります
乾燥を待つ
- のりが完全に乾燥するまで、ふすまを動かさないようにする。速乾性ののりを使用しても、一晩はそのままにしておくのが安全。
気候条件の考慮
- 湿度が高い日や極端に乾燥している日は、ふすま紙が伸縮しやすくなる。可能ならば、湿度が安定している日に作業を行う。
安全に注意する:
- カッターを使用する際は、手を切らないように注意する。
- 小さな子供やペットがいる場合は、誤って飲み込む小物がないか確認する。
予想施工時間
一枚あたりの施工時間ですが、本襖であった場合『枠の分解に10分』『下地処理と古い紙外しに15分』『紙切り5分』『貼り付け5分』『枠の結合に10分』を想定します。乾燥時間を抜かしても、慣れるまで1枚あたり45分程度は覚悟しておきましょう
<総括&所管>
ふすまの張り替えは、丁寧に行えばDIYでも十分に美しい仕上がりを期待できます。基本は慣れですが、、まず『本襖』『板襖』『段ボール襖』『発泡スチロール襖』の見極めが大切です(施工方法や貼り付け方法が異なるため)。今回は主に本襖での施工方法を記載させていただきました。ふすまの種類によって施工方法は全く違うため、くれぐれもご注意くださいませ!

特徴
・夫婦で貼替え職人をしています
・ご反響の電話には栗田洋子がでます、安心してご連絡くださませ
・見積もりには必ず私達が伺います
商材紹介
・襖張替え
保有資格
・宅地建物取引主任士
・ファイナンシャルプランナー
・証券外務員
・感染対策アドバイザー
・高所作業車操縦免許