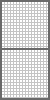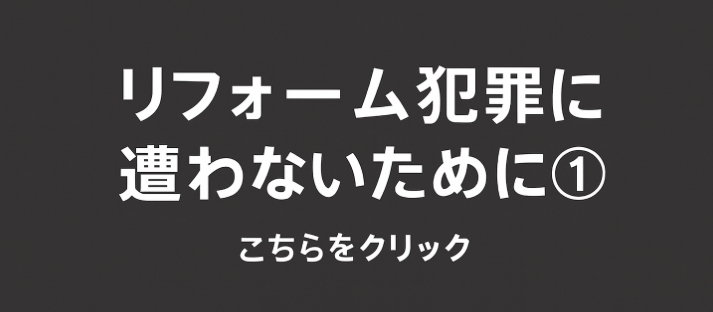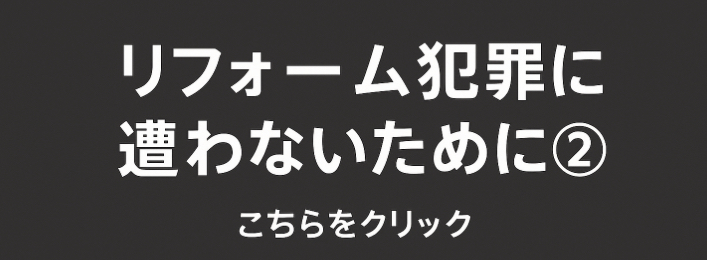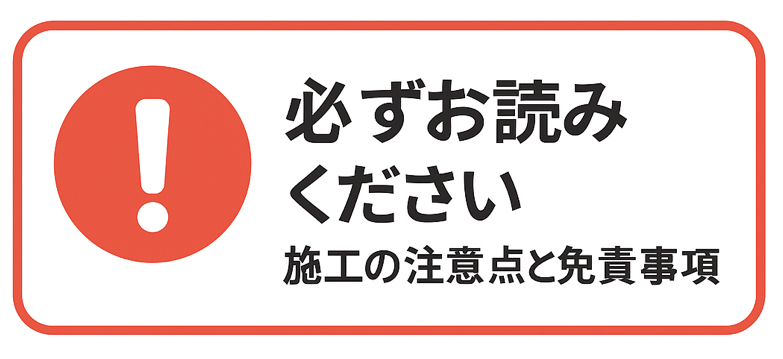畳の中国産と日本産の違い|品質差は?
はじめに
一昔前までは「中国産より日本産の方が良い」と言われていました。
しかし、近年は生産技術や管理体制が向上し、中国産畳表の品質は非常に高く安定しています。
実際、国内の多くの住宅や公共施設にも中国産畳表が採用されており、見た目や使い心地で大きな差を感じることは少なくなっています。
今回は、職人目線で「中国産と日本産の違い」をわかりやすく解説しながら、どちらを選んでも安心できる理由をお伝えします。
中国産畳表の現状:今は“安いだけ”ではない
中国では、い草の栽培から織りまでを専門に行う工場が年々増え、
日本の技術指導を受けながら品質管理を徹底しています。
以前は「色ムラがある」「折れやすい」などの声もありましたが、
現在は乾燥や泥染め(せんど)などの工程がしっかりしており、品質のバラつきは大きく改善されました。
✅中国産の主な特徴
- 価格が手ごろでコストパフォーマンスが高い
- 色や織りの品質が安定してきている
- 納期が早く、住宅リフォームなどにも使いやすい
- 一般家庭から旅館、公共施設まで幅広く採用実績あり
つまり今の中国産畳表は、**“手軽に使える安心品質”**に進化しています。

日本産畳表の特徴:やはり香りと風合いは別格
日本の代表的な産地は熊本県八代市(やつしろ)。
農家さんが一年以上かけて育てたい草は、一本一本が細く、しなやかで美しいのが特徴です。
✅日本産の良さ
- い草が細く、織り目が整っている
- 香りが強く、落ち着いた癒し効果がある
- 使い込むほどに艶が出て「味」が増す
ただし、品質が高い分コストも上がるため、
「本格和室」や「長く使いたい部屋」など、目的に応じて選ぶことが大切です。

職人が感じる「本当の違い」
見た目や肌触りだけで言えば、一般の方が中国産と日本産を見分けるのは難しいです。
実際、同じ等級(クラス)の畳表なら、
「織りの密度」や「色味の整い方」に多少の個体差がある程度で、
日常使いではほとんど差を感じません。
むしろ近年は、中国産でも日本の工場で最終検査を行う製品が増えており、
「国産ブランド仕様の中国産」というケースも多くなっています。
✅職人の感覚で言うなら
- “産地の違い”よりも、“織り手や選別の丁寧さ”の方が大事
- “価格の安さ”よりも、“どの部屋にどう使うか”で判断すべき
- “手入れの仕方”で寿命が何年も変わる
つまり、畳表は使い方とメンテナンス次第で寿命が決まる素材です。
どちらの産地を選んでも、丁寧に使えば10年以上美しく保てます。
比較表まとめ
| 項目 | 中国産畳表 | 日本産畳表 |
|---|---|---|
| 主な産地 | 四川省・安徽省など | 熊本県八代市 |
| 価格 | 手ごろで安定 | やや高価 |
| 見た目 | 均一で違和感が少ない | 自然な艶と風合い |
| 香り | 控えめ | 強く香る |
| 耐久性 | 5〜8年 | 7〜10年 |
| 向いている用途 | 一般住宅・リフォーム・賃貸 | 新築・本格和室・茶室 |
結論:今の中国産畳表は「安心して使える品質」
昔のように「中国産=低品質」という時代ではありません。
現在の中国産は、日本の技術をもとに生産された安定品質の畳表です。
見た目も美しく、施工後の仕上がりで差を感じることはほとんどありません。
- 「費用を抑えたい」方には中国産で十分
- 「香りや風合いを楽しみたい」方には日本産がおすすめ
どちらも正しい施工とお手入れがされていれば、長く快適に使えます。
畳は“どこで作られたか”よりも、“どう使い、どう暮らすか”。
その人の生活スタイルに合わせて選ぶことが、一番のポイントです。
当店の特徴
その1・夫婦で貼替え職人をしています
その2・ご反響の電話には栗田洋子がでます、安心してご連絡くださませ
その3・見積もりには必ず栗田が伺います
その4・(社)茨城県南職人協会の理事であり工事の健全化に努めています
商材紹介
・襖張替え
お客様の声というコンテンツへの弊社の思い
当店ではHPに【お客様の声】というページを作っていません。その理由とは
保有資格
・宅地建物取引主任士
・ファイナンシャルプランナー
・証券外務員
・感染対策アドバイザー
・高所作業車操縦免許